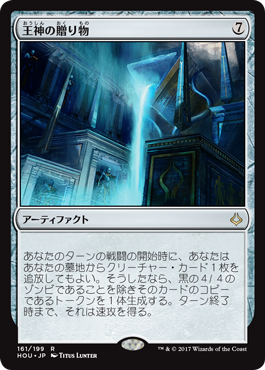オケチラ最後の慈悲/Oketra’s Last Mercy
「初期ライフ総量」という訳語が入った 3 枚目のカード。しかし、ゲーム開始時のライフの量を参照するカードとしては 7 枚目だったりする。英語の “starting total life” という表現の訳が《毅然たる大天使/Resolute Archangel》が出るまでいろいろと揺れてたため、このような齟齬が起きたようだ。《毅然たる大天使/Resolute Archangel》の次に出た《極上の大天使/Exquisite Archangel》でも「初期ライフ総量」と訳されたことで、訳語がこれに決まったらしい。初期ライフ総量を参照6枚のカードのうち、ライフを元に戻すという能力がこれらのカードで共通していることが、安定化に一役買ったような気もする(主に検索能力的な問題で…)。もちろん妄想ですよ。
ちなみに、ライフを初期値に戻す(ような)過去のカードとしては《清めの風/Blessed Wind》がある。これはライフを 20 点にするので初期値に戻すわけではないけど、9 マナとやたら重いカードになっている。相手にも使える点が評価されているのか、ライフを戻す能力自体が高く評価されたのか、当時のことはわからない。ただ、自分のライフを戻す能力については、このカードでは(デメリットがあるとはいえ) 3 マナに設定されたので、かなり弱めの能力と最近は判断されているようだ。
これくらい軽くなると、《群れの統率者アジャニ/Ajani, Caller of the Pride》とか《群れの統率者アジャニ/Ajani, Caller of the Pride》、《死の宿敵、ソリン/Sorin, Grim Nemesis》の大マイナス能力の直前に使う、みたいな運用ができるかもしれない。多人数戦でやったら 40/40 のトークンが出てきたり、1/1 絆魂が 40 体並んだりしてなかなか楽しそう。そんなのが出てきたら、次のターンに土地がアンタップしなくてもあんまり痛くない。ひっそり《永遠の器/Eternity Vessel》を出しておけば、何回も同じことができる。《失われし夢の井戸/Well of Lost Dreams》を出しておけば、大量にカードも引けそう…さすがにマナがないかな。ただし《加護の反射/Boon Reflection》を出しておくと、ルールの解釈で一悶着起きそうな予感も。