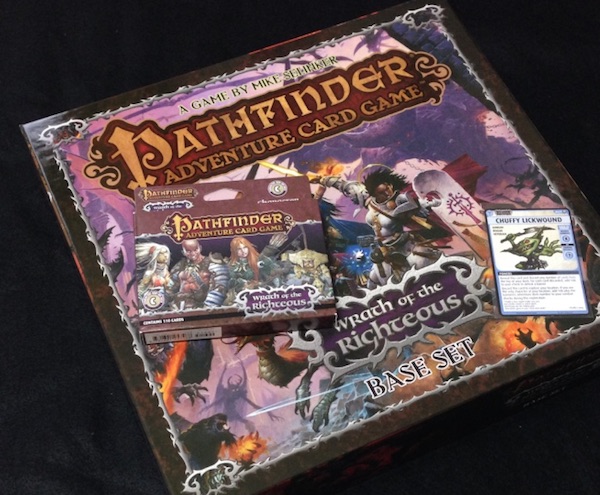Android Netrunner は二人用のデッキを用いるカードゲーム (Living Card Game: LCG) で、プレイヤーはコーポレーション(サーバの防御者)とランナー(サーバへの侵入者)のいずれかを担当する。
コーポレーションは、サーバを使って「計画ポイント(アジェンダポイント)」を作る能力をもっている。コーポレーションは 7 ポイント作ることができれば勝利となる。「計画ポイント」は、電子的な価値のある情報のようなもので、今風にいえば「ビットコイン」みたいなものだ(と思う)。これに対して、「計画書」はビットコインを作るプロジェクトの計画書のようなもので、決められた回数だけアドバンス(計画を実行)させると、カードに書かれている「計画ポイント」を得ることができる。
一方で、ランナー(侵入側)はサーバに侵入する能力を持っており、サーバから「計画書」を盗むことで得点できる。ランナーは、コーポレーションから7 ポイント盗めたら勝ちになる。ランナー側は単に「計画書」を盗めばよく、「アドバンス」という操作をする必要はない。そのかわり(?)、自力では「計画書」を作ることができない。
上の写真の、左が「ランナー」を示す ID カードで、右が「コーポレーション」を示す ID カード。ID カードはデッキには入れず、最初から場に出して使う。ランナー側もコーポレーション側も複数の種類の ID カードがあり、カードによって能力が異なっている。また、使用する ID カードによってデッキに入れられるカードの種類にも制約がつく。だから、デッキを組むよりも前に、どの ID カードを使うかを選択する必要がある。
これが「計画書」カード。コーポレーション側のデッキにしか入れられない。コーポレーションはこのカードに対して「アドバンス」という操作をして得点にし、ランナーはこのカードをコーポレーションから奪って得点にする。
カードの右上に、ポイントを得るまでに必要になるアドバンスの回数が書かれている。これらのカードの場合、ポイントを得るには「4回」のアドバンスが必要ということを示している。
カードの中段左側に書かれている数字が「計画ポイント」で、コーポレーションは計画書を完成させると 2 ポイント得られ、ランナーはこのカードを盗むことで 2 ポイント得られることを示している。
コーポレーション(防御側)の戦略
コーポレーションには、最初から R&D、HQ、アーカイブという3種類のサーバがある。といっても、これらは「山札」「手札」「捨札」のことで、このゲームでは山札のことを「R&D」、手札のことを「HQ(ヘッドクオーター)」、捨札の束のことを「アーカイブ」と呼ぶことになっている。いずれにしろ、これらのサーバではビットコイン(計画ポイント)は作れない。
じゃあどこで作るかというと、「遠隔サーバ」というところで作ることができる。「遠隔サーバ」というのは、コーポレーションが自分の手番に、手札のカードを裏向きに出す(インストールすると言う)ことで作ることができる。
ランナー側からコーポレーション側の陣地を見ると、上の写真のようになる。山札の横に、裏向きに置かれたカードが「遠隔サーバ」である。この「遠隔サーバ」に対して、自分の手番のときに「アドバンス」という操作をすることで、計画ポイントを作ることができる。ちなみに、遠隔サーバはいくつでも作ることができる。
「アドバンス」という操作は「ビットコインを作る計画を実行する」というような意味だと思ってもらえば、だいたいあってる(気がする)。コーポレーションは、「遠隔サーバ」のカードに書かれている回数だけ「アドバンス」すると、カードに書かれたポイントの分だけコーポレーションの得点になる。
アドバンスした遠隔サーバには、円い「アドバンストークン」を置いて、何回アドバンスしたか分かるようにする。遠隔サーバは裏向きのままでもアドバンスできるし、何らかの理由で表向きの状態になっていてもアドバンスできる。
つまり、コーポレーションとしてはひたすら「遠隔サーバ」を作って「アドバンス」しまくれば勝てる、ということになる。
ランナー(侵入側)の戦略
一方、ランナーは自分では計画ポイント(ビットコイン)が作れない。その代わり、コーポレーションのサーバに侵入して「計画書」を盗み、ポイントを得ることになる。
ランナーは自分の手番に、コーポレーション側の好きなサーバを指定して「ラン」する(侵入を試みる)ことができる。ランに成功してサーバにアクセスできたとき、それが「遠隔サーバ」だったときは、コーポレーションはそのカードを表向きにしてランナーに見せる。
アクセスされたカードが上のような「計画書」だったときは、ランナーにカードを奪われてしまう。そして、表に書かれた「計画ポイント」の分だけ、ランナーがポイントを盗んだことになり、それがランナー側の得点になる。たとえば上のカードの場合は、いずれを奪った場合でも 2 ポイントがランナーの得点になる。取引所のサーバに侵入してビットコインを盗む、みたいなことを想像してもらえば、だいたいあってるかも。
だから、ランナーは「サーバ」にランして計画書を盗みまくることで勝利を目指す。