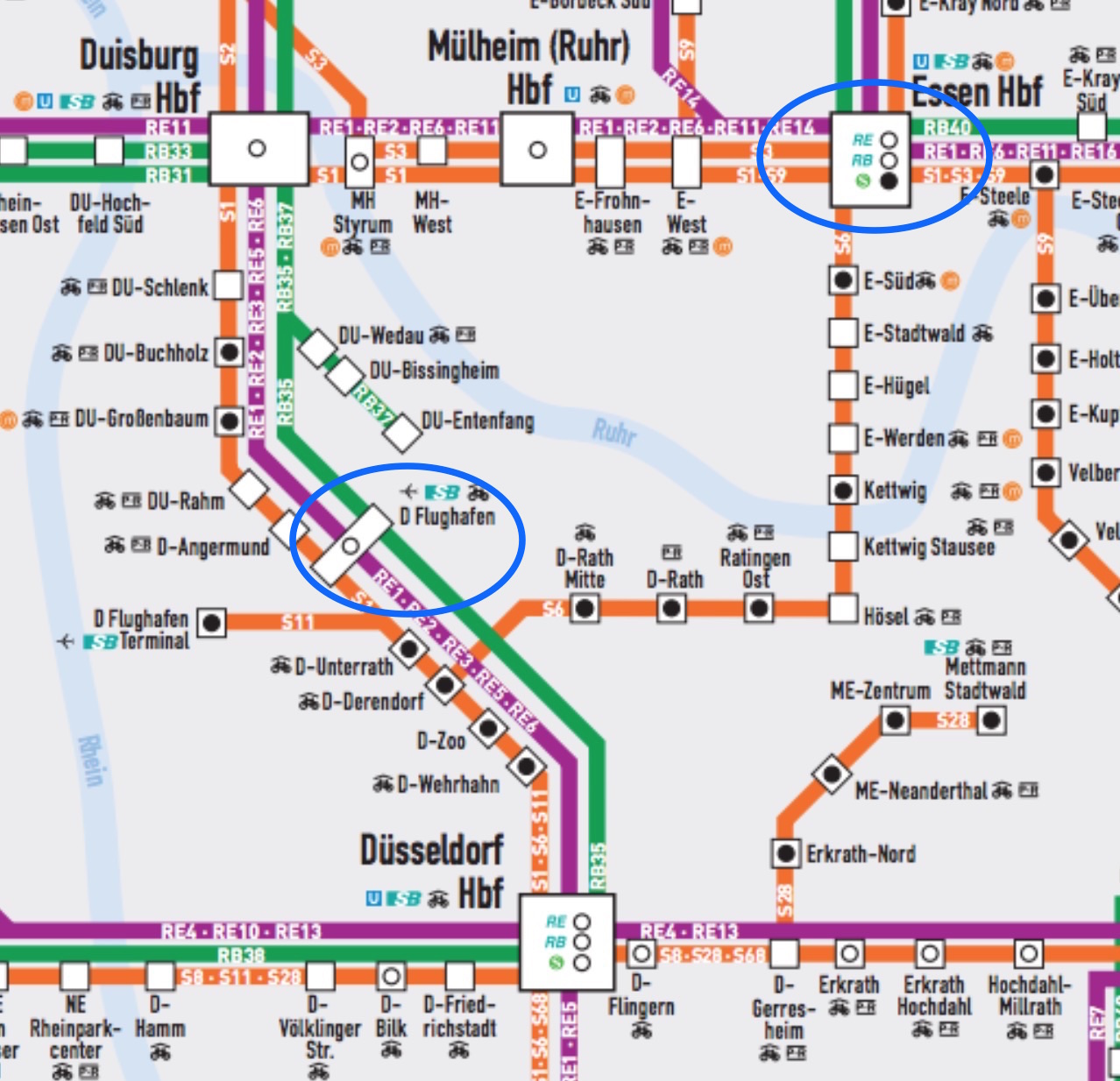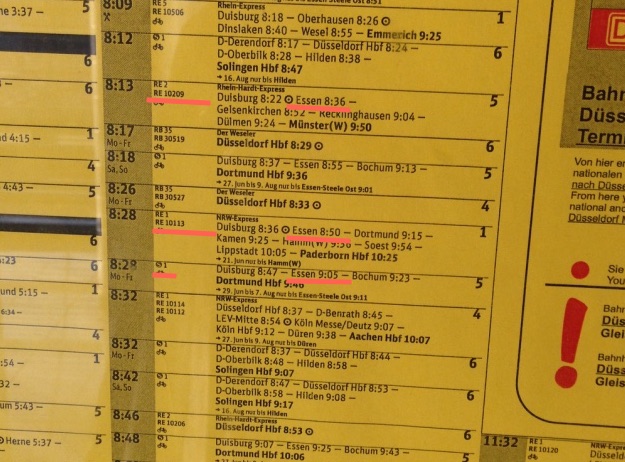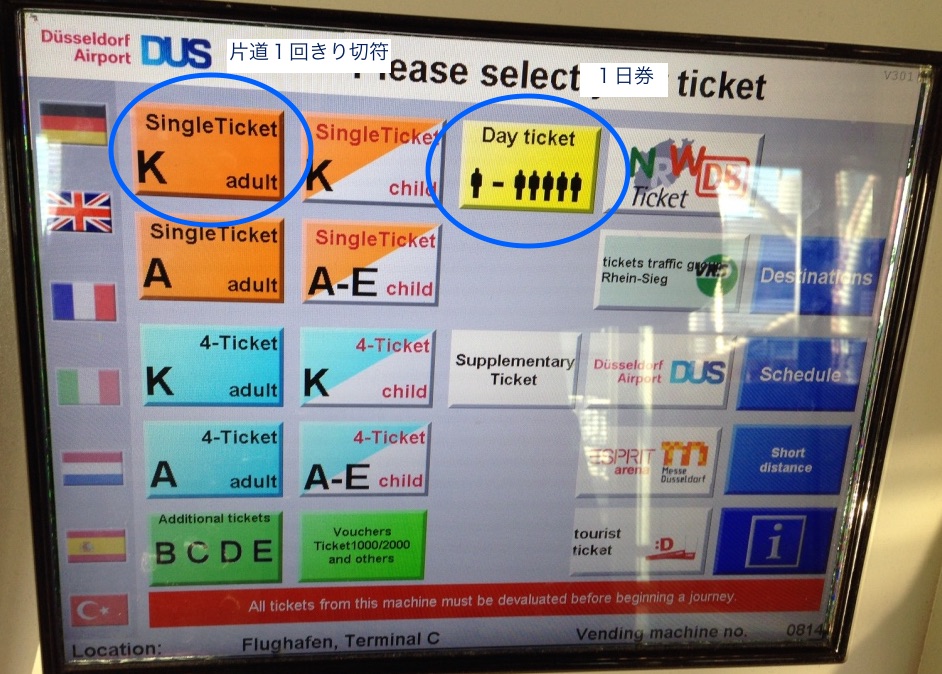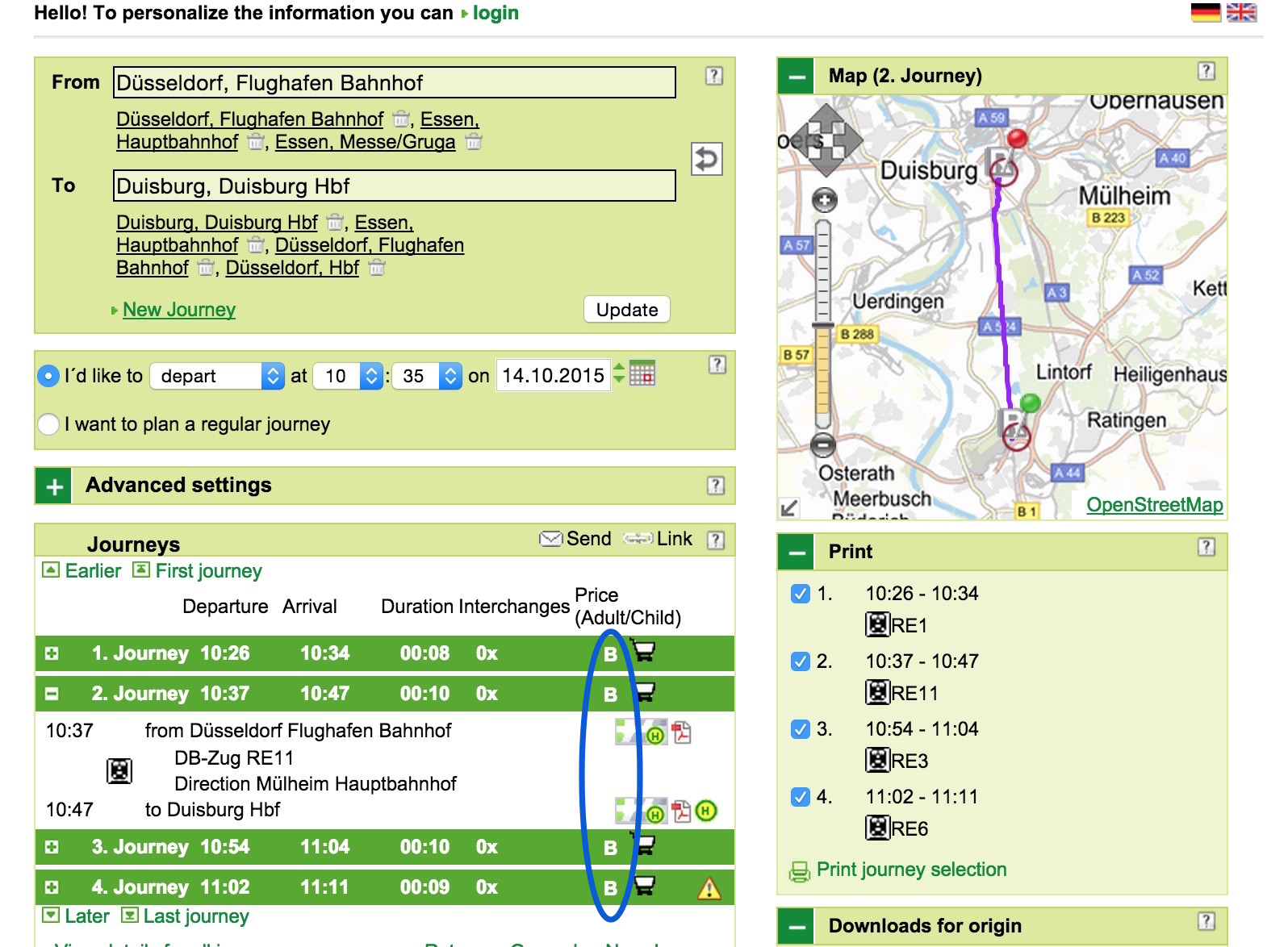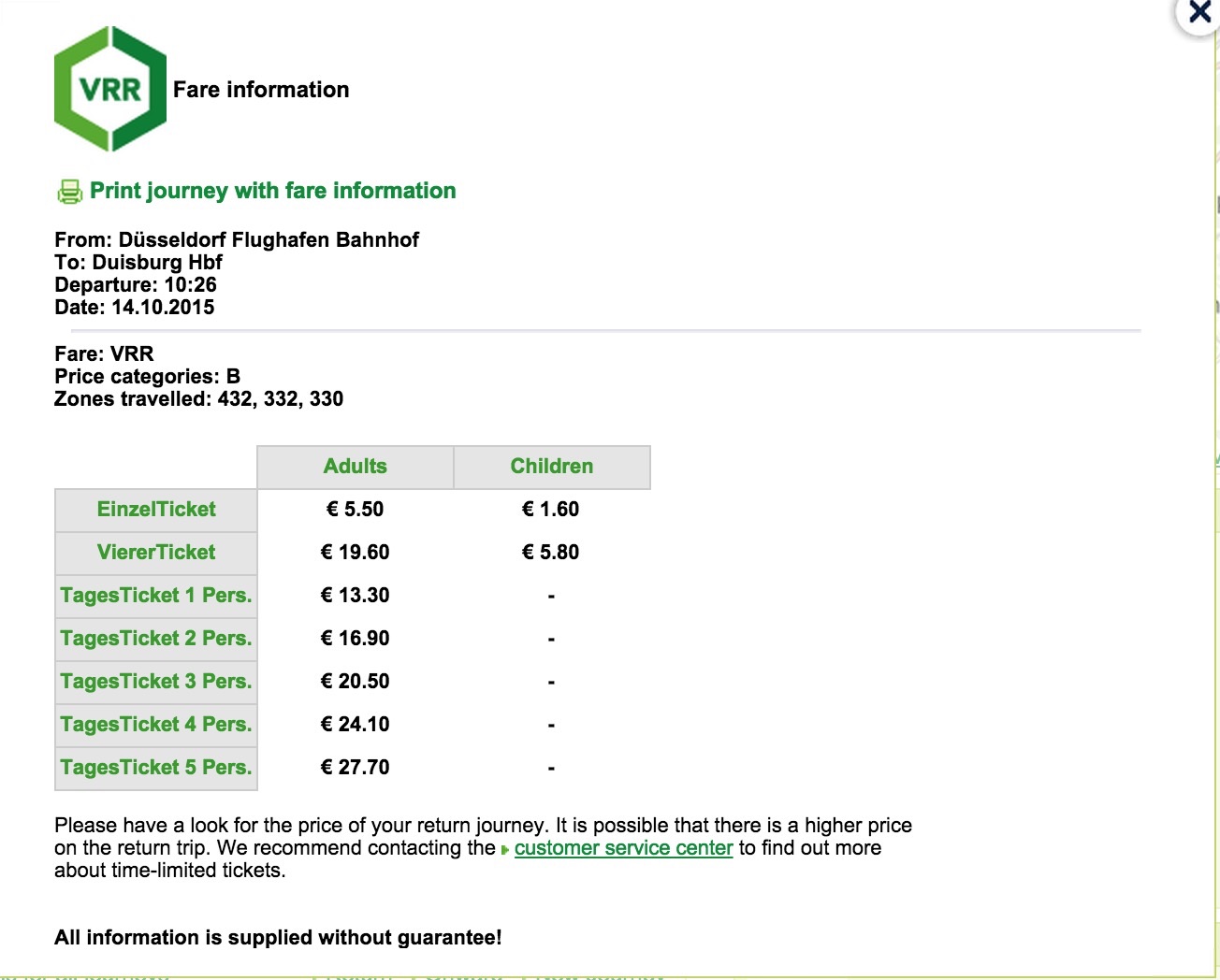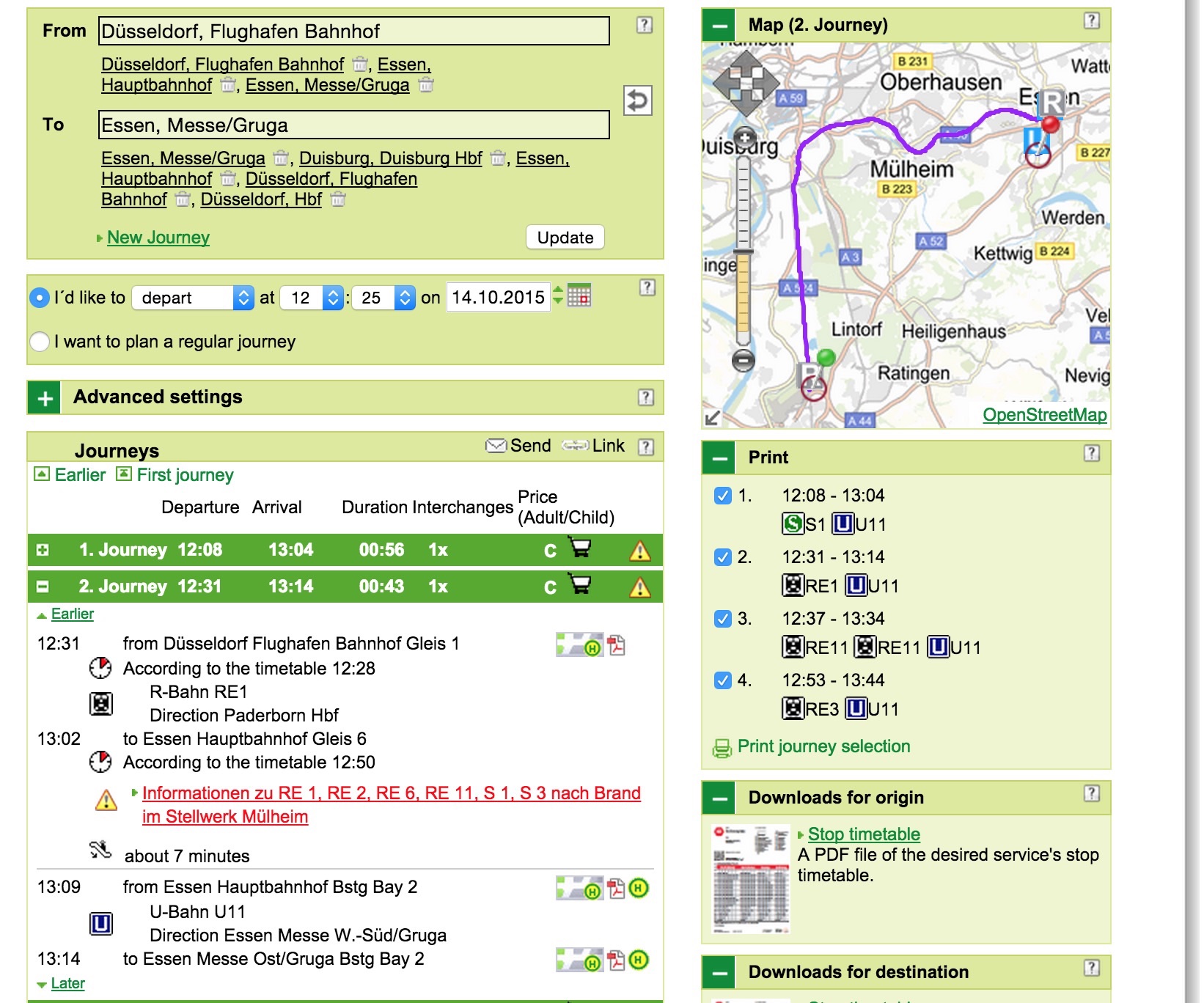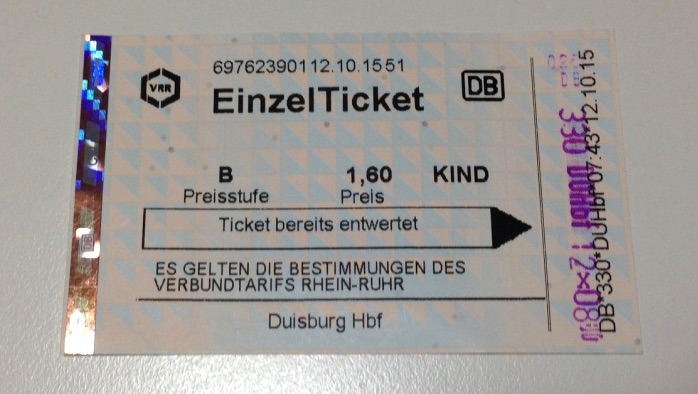Epic Card Game は、Star Realm を作っている White Wizard Games が 2015 年に発売した対戦型のカードゲームである。プレイヤーはそれぞれ、120枚のカードからランダムに選んだ30枚のカードをデッキとして使用しする。そして、先に相手の30点のライフポイントを削りきるか、ライブラリーアウトさせれば勝ちとなる。
雰囲気としては「時間や金がなくても手軽に遊べるライトな Magic the Gathering」といった感じ。デッキ構築がない分 Hearth Stone よりさらにライトな感じがする。ルールもシンプルで教える手間も少ないので、「ちょっとした空き時間に気軽にプレイする」対戦型カードゲームとしては良い感じ。
カードについて
このゲームで使うカードには「イベント」「チャンピオン」「トークン」の三種類がある。
「イベント」は使うとその場で効果を発揮するカードで、基本的に1回しか使えない。
「チャンピオン」は場に残るカードで、攻撃や防御をしたり、カードに書かれた能力を使うことができる。チャンピオンのカードは、左下の赤いマークのところに攻撃力が、右下の青い盾マークのところに防御力が書かれている。
「トークン」はイベントカードやチャンピオンの能力などで場に出るカードで、山札に入れたり捨札にならないという以外は「チャンピオン」とほぼ同じ機能をもつ。
右肩に黄色で 1 と書かれているカードは、プレイするときに「ゴールド」を支払う必要がある。この「ゴールド」は、各ターンのはじめに各プレイヤーがひとつずつ獲得する。次のターンの始めにゴールドは消えてしまうので、ターンを越えてゴールドを持ち越すことは、基本的にはできない。また、ゴールドは場に出ている「チャンピオン」の能力を使うときに支払うこともある。
なお、ターンをプレイしているプレイヤーだけがゴールドを得るのでなく、すべてのプレイヤーがゴールドを得るという点は間違いやすい。つまり、自分のターンではないときでも、ゴールドを使ってカードをプレイしたり、能力を使えるタイミングがある。
また、カードには属性(alighment)がある。赤青緑黄の4つの属性があって、特定の属性のカードを対象にする能力をもつカードがあったりする。ただし、MTG のように「色マナ」みたいなものはない。
プレイの流れ
このゲームはターン制で、自分と相手が交互にターンをプレイする。ターンは「ゴールドを充填する」「カードを1枚引く」「カードのプレイや攻撃、パワーの使用を行なう」「ターンを終了する」という流れで行なう。
最初に、各プレイヤーがゴールドをひとつ得る。前のターンで使わず残っていたゴールドは消えてしまうので、基本的にはひとつだけゴールドを得た状態になる。
次に手番のプレイヤーは手札を 1 枚引く。これは強制で、もし引けなければ負けになる。そして、手番プレイヤーのチャンピオンのカードを全て「アンタップ状態」にする。
手札を引いたあと、手番のプレイヤーは「イベントカードを使う」「チャンピオンカードを場に出す」「場に出ているチャンピオンカードのパワーを使う」「攻撃する」のうちから、好きな行動を好きな順序で実行していい。
攻撃を選んだときは、「攻撃するカードを選ぶ」「(相手が)防御に使うチャンピオンカードを選ぶ」「ダメージを与える処理をする」という手順で戦闘フェイズを実行する。戦闘フェイズの間に、各プレイヤーがカードや能力を使用できるタイミングがある。
攻撃に使えるチャンピオンは「アンタップ状態」(このゲームではpreperedという)で、なおかつ「今のターン以前から場に出ているもの」である。チャンピオンは、MTGで言うところの「召喚酔い」をする。防御できるクリーチャーは「アンタップ状態」のものであれば可能で、召喚酔いは影響しない。このあたりは MTG とほぼ同じ。能力の起動に「タップ」を必要とするものについても「今のターン以前から場に出ているチャンピオン」しか使えない。このあたりも MTG と同じ。
防御に使ったチャンピオンは上下さかさまの状態(flippedという)にして置く。この状態のチャンピオンは、タップを必要とする能力は使えるけど、再度防御に割り当てることはできない。
ちなみに、チャンピオンが攻撃できるのは MTG と同様に「相手プレイヤー」だけで、遊戯王のように相手側のチャンピオンカードを直接指定して攻撃することはできない。
手番のプレイヤーがすべての行動を終えたとき、相手プレイヤーがカードや能力を使えるタイミングがある。もし相手が何かをしたら、再度手番のプレイヤーがカードを使ったり攻撃したりする機会を得る。もし双方とも何もしない(できない)なら、ターンを終わる。
だいたいこんな感じ。
Magic the Gathering との比較
上に書いたように、ルールは MTG によく似ている。MTG から複雑だったり手間がかかる部分を除去した感じ。相違点はだいたい以下の通り。
- デッキを構築しない(ランダムな30枚のカードをデッキにする)
- カードのプレイ時に払うコストが「何も無し」または「1ゴールド(無色のマナのようなもの)を支払う」の二種類しかない。ゴールドは自動的に毎ターン補充され、翌ターンに持ち越せない
- 「スタック」のような概念がない。能力は直ちに解決され、相手に妨害されるタイミングはない。
- カードの種類は「イベント(=インスタント)」「チャンピオン(=クリーチャー)」の二種類だけ。
- 自分の手番に、何度でも戦闘フェイズを実行できる。
- アンタップ状態、タップ状態に加えてフリップ状態(カードを防御に使えない)というのがある。
- 初期ライフは 30 ある。
デッキ構築という概念がないので、構築にかかる手間が必要なく、またカードを大量に集める必要もない。時間や金がない人でも気軽に遊べるのはいいところ。またスタックの概念がないことから、相手に自分の行動を阻害されることがなく、自分のターンの行動の計画が立てやすい。
一方で、使用するデッキのカードをランダムに選ぶことから、運ゲーになってしまうこともあり、また長期的な戦略に基いてプレイする、みたいなことはできない。その時々の手札や場の状況に基き、臨機応変にプレイしていくという感じになる。
ただし、ドラフトでデッキに入れるカードを選ぶ遊び方もあるので、「デッキ構築」を楽しむことも可能ではある。
以上、研究員Kからルールの解読を丸投げされたので、ざくっとルールブックを読んだ内容を書いてみた。ざっくりすぎて、どこか間違っている可能性もあり。