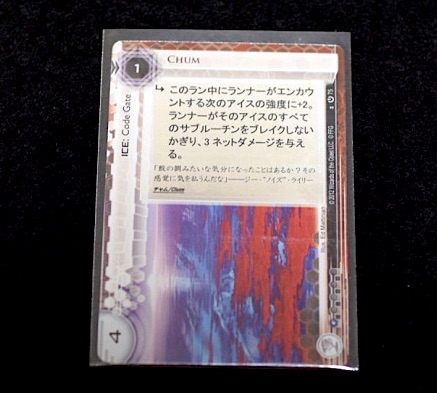マラキールの解放者、ドラーナ/Drana, Liberator of Malakir
マラキールの解放者、ドラーナ/Drana, Liberator of Malakirいろいろな意味で《呪われたミリー/Mirri the Cursed》を思い出したカード。飛行、先制攻撃つきで、サイズもコストも同じくらい、戦闘ダメージを与えると +1/+1 カウンターを載せるといったあたり、ミリー先生によくにている・・・んだけど、細かいところで結構違っている。単体のカードとしてはミリー先生のほうが使いやすいけど、デッキを底上げするカードとしてはドラーナ先生のほうに軍配が上がるという感じかな。ただ、伝説なので複数並べられないのは残念なところ。
ちなみに、能力とサイズだけ見たら《流城の隊長/Stromkirk Captain》のほうがより近い。こちらは飛行をもっていないかわりに、ダメージを与えなくても全体強化ができる。しかし、カウンターを載せるのではなく +1/+1 の修整を与えるという点と、強化できるのは吸血鬼だけというところで、また使い勝手が違っている。
というか、本当は過去のドラーナ先生からの変遷を書こうと思ってたんだけど、ドラーナ先生がライザップに行った説が面白かったので、ここではパス・・・
 水の帳の分離/Part the Waterveil
水の帳の分離/Part the Waterveil(2)(青)というコストで 6/6 速攻のクリーチャーを出せると思えば、かなりコストパフォーマンスは良い。他の +1/+1 カウンターを 6 個置けるカードと比べても、このコストは相当に安い。たとえば、エンチャント先のクリーチャーに +1/+1 カウンタを 6 個載せる《ウィーティゴの姿/Shape of the Wiitigo》のコストは(3)(緑)(緑)(緑)となっている。X個のカウンターを載せるカードを見ても、一番安そうな《膨らむ勇気/Swell of Courage》でもコストは(X)(白)(白)なので、6つ載せるには 8 マナもかかる。今のところ、他の「覚醒」カードと比べても(カウンターを載せることに対する)コストパフォーマンスは良い。
とまあ、カウンター部分についてはとても良いんだけど、追加ターンをプレイできるカードとしては、それほどコストパフォーマンスは良くないのよね。使うと追放されてしまうし。やはり覚醒のほうをメインにして《樹上の村/Treetop Village 》とか《天界の列柱/Celestial Colonnade》みたいな、大き目のミシュラランドと組合せて一瞬で撲殺、みたいな感じにしたいところ。

 粗暴な排除/Brutal Expulsion
粗暴な排除/Brutal Expulsion 果てしなきもの/Endless One
果てしなきもの/Endless One